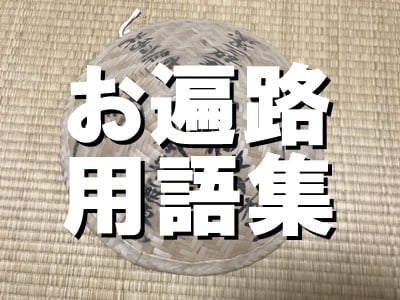お遍路用語集
お遍路さんの専門用語、用語を紹介します.
お遍路
弘法大師様が修行で歩んだ、四国1400kmの旅。元々は修行僧による厳しいものでしたが、江戸時代に今で言う『旅行ガイドブック』が発刊され、ブームになったと言われています.
同行二人
『常に弘法大師様と一緒』という意味があり、一緒に歩いて修行をしているということです。修行中はすぐ横にいるのでアホなことはできません.
順打ち
1番さん霊仙寺から、88番大窪寺まで、四国を時計回りに順番にお参りする方法.
逆打ち
88番、大窪寺から、四国を反時計回りでお参りする方法.道中の道が険しいということで,順打ちの数倍ご利益があると言われています.特にうるう年の逆うちはさらに倍・・・クイズダービー的な効果があるようです。また、車お遍路ですと、道が険しいだけでなく、情報も少ないので迷いやすいです.しかも、一般的な順打ち遍路さんから逆行することになるので、細い道でのすれ違いが多くなります.特に朝1番、2番のお参りは確実に逆方向からくる何台もの順打ちの車とすれ違いますので、かなり神経をすり減らすお参りになります.
通し打ち
1から88札所まで一気に周ること.
区切り打ち
1から88を小分けにして周ること。1県ごとは『1国参り』といいます.
納経帳(のうけいちょう)
四国お遍路のお参りで、ご本尊さまとお大師さまにお経を奉納のした証として納経所で御朱印を頂く帳面のことを『納経帳』といいます.古くは写経をした証だったようですが、あくまで、修行の一環で行うお経の奉納の証ですので、趣味のお寺巡りの際に使う『御朱印帳』とはちょっと意味合いが違います.八十八ケ所を全てお参りする心積もりがある場合はお遍路さん専用の『納経帳』を準備しましょう.
先達(せんだつ)
四国お遍路、八十ハヶ所を何度も巡業してる達人のことを”先達”と言います.なんとなく雰囲気で分かりますが、納札色がついていると”先達”と思っていいでしょう.
白(1~4巡)
緑(5~6巡)
赤(7~24巡)
藍(25~49巡)
金(50~99巡)
特注品(100回以上)
となっています.赤はたまに見ますね.
お接待
管理人は車移動のお遍路なので、本物のお接待を受けたことはありません.地元の人が食べ物や飲み物を施すことを”お接待”といいます.もし、お接待を受けた場合は納札を渡すというのがマナーとなっています.納経所でお接待を受けられる場所が数か所あります.
結願(けちがん)
88ヶ所、最後にお参りしたお寺さんを”結願寺”などとも言うそうなのですが、88ヶ所全てのおを周ることを”結願”と言います.