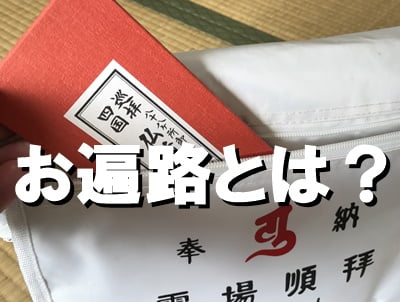お遍路って何?
若いときにはまったく興味のなかったお遍路の旅.意味が分からなかった旅なのですが、一番分かりやすいのが巡礼グッズのバックに書かれている『同行二人』の意味を考えるところからではないでしょうか.恥ずしながら、私もこのあたりの意味がまったく分かっていませんでした.同行してくれるのは弘法大師(真言宗の宗祖)、後の空海です.弘法大師様と四国八十八ヶ所を巡礼し、自分を見つめ直す旅という人が多いようです.修行や、供養など、ひとそれぞれ、さまざまな理由で巡礼するようです.
お遍路のマナー
目的は人それぞれですが、巡礼者は同じ旅人仲間と考え、道中の仲間の無事を願い、気遣い合うというのがマナーとなっています.それほど多くないですが、最低限のマナーやルールを紹介します.
・境内は左側通行
・菅笠以外の帽子は参拝、納経所で脱ぐように
・読経、参拝は端っこで
・鐘はできるだけ優しく撞く(近所迷惑にならないように)
・お賽銭は投げ込まず、そっと入れる
・ローソクはできるだけ奥側に
・手水場でお清めで使った柄杓の柄は残った水で清めよう
・トイレと食事のときは輪袈裟を外す
・橋を渡るときは金剛棒を地面に突かない
などがあります.
お遍路の歴史
邊地(へち)信仰→邊路(へじ)→遍路となったようです.邊地(へち)信仰とは特に四国だけでなく、吉野(奈良)や熊野(和歌山)などで修行して信仰を深めることだったようです.そんな中、弘法大師が四国の厳しい自然四国で修行し、6年目に室戸岬で悟りを開いたそうです.その際に四国各地で開いた寺は39ヶ所になります.(88ヶ所ちゃうんか!突っ込み)その後、弘法大使は高野山い入定したようです.弟子たちにより弘法大師信仰が説かれるようになり、当初は行者や修行僧が四国を巡業するようになったようです.そこから徐々に一般庶民にも広がるようになり、江戸時代に、今でいうガイドブック(『四国辺路道指南』しこくへんろみちしるべ:真念)が発行され、現代の四国お遍路の同行二人(どうぎょうににん)の旅の原型ができたようです.さらに、邊地(へち)信仰→邊路(へじ)→遍路と、一般的な表記になったのもこのころのようです.
四国お遍路はなぜ88ヶ所なの?
いろんな説があるようです
・厄年の合計 男42+女33+子供13
・お釈迦様が説かれた法から説
・煩悩の数
・お米の漢字を分割した説
などがあります.